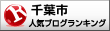<投稿基準日:2023/3/29:20230329>
持病の膵炎、コロナの後遺症のための頭痛があってなかなかすすまない積ん読本の読書、気持ちの余裕が出来て、いっきに読んでおります。
読書後体調が徐々に悪くなり、読み終わった本が再び積ん読本になり、入院療養終了後現在お片づけ中。
蔵書の他に保管に回しているパンフレット類の一部

CSRと調べると、企業の社会的責任と出てくる。社会的責任の自己PR的な広報資料なのだが、元々道路公団という国営企業の株式会社で何が変わってきているか注目しているところである。
<パンフレット内容とブログ本文は私見なので全然違います>
民営化と言っても旧3公社(1985年電電公社専売公社、1987年国鉄)や郵政とは違い、株式の売却で国の財政に寄与する意図が無いことが根本的に違っており、単純に国鉄改革などとの比較は出来ない。
道路公団民営化のスキームとして『高速道路保有債務返済機構』の存在があって、公団改革として『不採算路線の新直轄化』として公団継承会社の新規建設は抑制されたかに思われるが、改革時に始めから解っていた次のような事項が顕在化しつつあると私の私見。
・高速道路土木資産の大規模更新(全国網)
・東名阪、首都圏での新規路線の投資規模が大きすぎた
・山岳路線では、トンネルの更新周期が短かったり、開通後の災害経験を受け、暫定2車線区間では安定した運用が見込めず、利用が少ない路線でも4車線化する必要に迫られた
・道路公団を解体する際、『道路公団(全国網)』『道路公団(地域網)』『首都高』『阪神高速』『本四公団』の資産債務継承法人が同じになってしまい、会計上の取扱が非常に解りにくい
・『本四公団』と『東京湾横断道路(株)への分割払建設費』が、旧道路公団の承継債務とは別にカウントされているのではと思われ、大規模更新時に明らかになるであろう『追加承継債務(大規模更新分)』が、特殊構造ゆえの他の土木構造の路線より相当大きくなるであろう。
と言うことで、国策事業での利用料割引があったり、災害時などは、次年度以降に遅れてNEXCOへの貸付料が減免され、遅れて高速道路機構への補助金と言うカタチをとらず、高速道路機構の債務が国庫に差し替えられたりと、非常に国民に解りにくい制度になっており、昨今の報道だと、大規模更新時の費用を理由に高速道路無料化は止めたと同様の償還期限が設定されたりと、NEXCOのせいでは無いが、道路公団改革時の精神が骨抜きにされていると思われ残念です。
NEXCOは分割されたと言え、経営法人が別であるほか、
・利用上利用者がその会社区分を意識せず利用出来ること。
・JRのように資材調達を短期的な安さを求めることをせず、会社分割をしたものの共通資材利用を進めていることで、公共インフラの災害時対応資材融通と言った基本的なことは確実に守られており評価に値する。
NEXCO東日本については、他のNEXCOの動向(本四債務の全国網組み入れなど)に今後も左右されないことが最大の地域貢献だと思う。